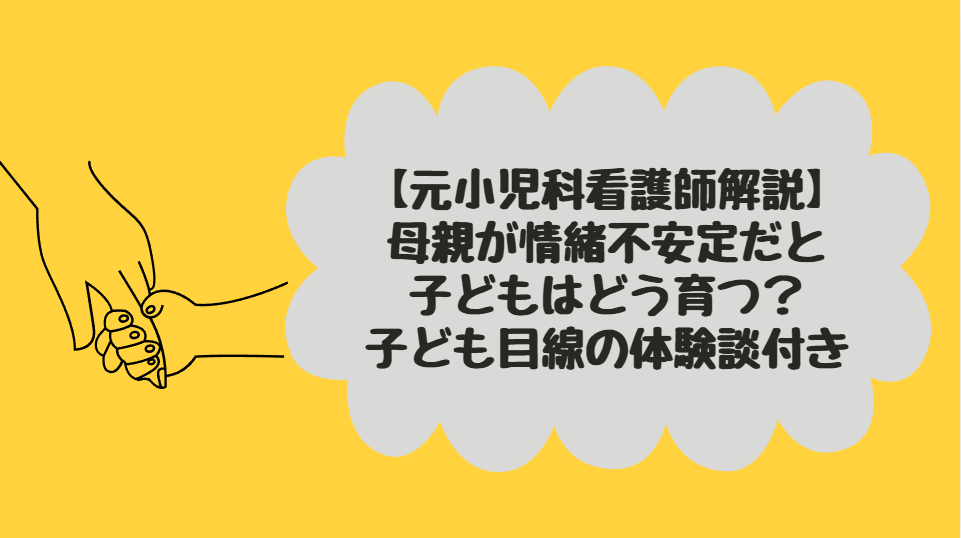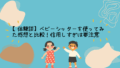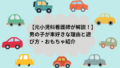「忙しさからイライラして、つい子どもに当たってしまった…」
「強く叱ったせいで、子どもに嫌われないか心配…」
「イヤイヤ期で、どう接したら良いか分からない…」
このような子育てに関する悩みは、母親であれば誰もが経験するでしょう。
夫婦共働きが普通になった現代では、女性の負担が増えているケースも多く、そのストレスやイライラを子どもにぶつけてしまうことも少なくありません。
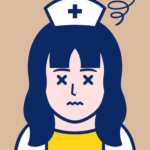
私も、時間が迫っている朝などは特に、
「早く準備して」
「もう置いていくよ!」
と声をかけてしまった経験が何度もあります。
しかし、母親の情緒不安定を子どもにぶつけてしまうと、子どもの成長を妨げる原因となることが複数の研究で明らかになっています。
本記事では、ワンオペ育児中の看護師である私が、医学的な根拠をもとに子どもとの上手な接し方を解説します。
- 母親の情緒不安定が子どもに影響する理由
- 母親のイライラが子どもに向かってしまう原因
- 情緒不安定になったときの子どもとの接し方
- 情緒不安定な母親を持つ子供の気持ちと悩み
子どもとの接し方に悩んでいる人、つい子どもに当たってしまった経験がある人は、本記事を通して、子どもの気持ちを理解した対応ができるようになりましょう。
【医学的根拠あり】母親の情緒不安定が子どもに与える影響
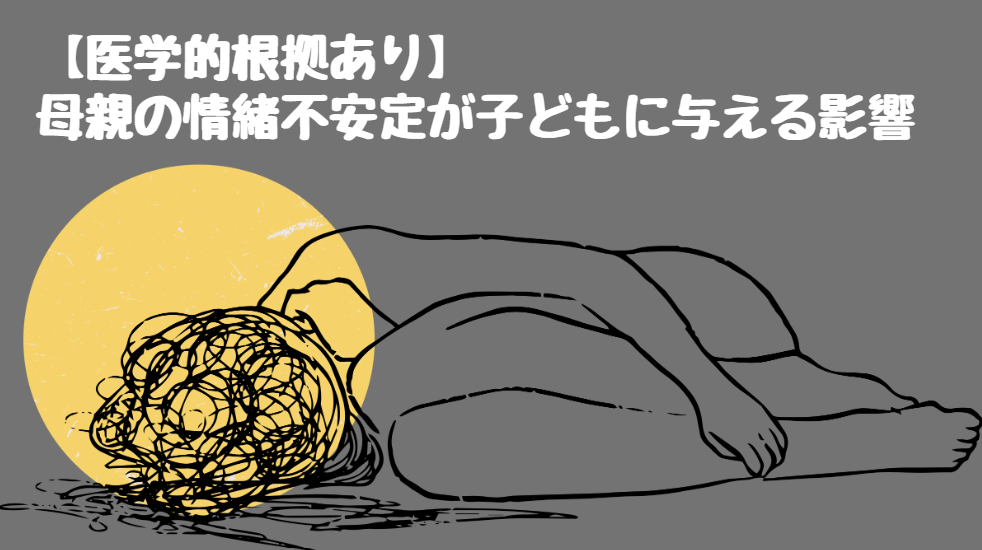
冒頭でも伝えたように、母親の情緒が不安定だと、子どもの成長に悪影響があると知られています。
子どもにとって一番身近な存在は母親であり、子どもは母親の行動をよく観察しています。

「気付いたら自分の口癖をよく真似している」
「怒り方が自分と一緒」
という場面に遭遇した経験がある人は多いのではないでしょうか?
次の内容では、母親の情緒不安定が子どもに与える5つの影響を解説したので、この機会に学んでみてください。
- 子どもは無意識に母親の感情を真似する
- 愛着形成に悪影響が出る可能性がある
- 家庭の雰囲気が子どもの安心感に直結する
- 過干渉や無関心は発達のリスクになる
- ストレス環境が脳や神経の発達に影響する
子どもは無意識に母親の感情を真似する
「親がいつも怒っていると、怒りっぽい子どもになる」
「親が悲観的だと、子どももネガティブになる」
というように、子どもは無意識のうちに母親の感情を真似して育ちます。
子どもは自分の感情をまだ上手に言葉で伝えられないため、母親の感情表現をお手本にその感情を学んでいるのです。

特に赤ちゃんの頃や幼稚園に通うような年齢のときは、母親の表情や声、反応から感情を学ぶ時期といわれています。
母親が安定した情緒で接していると、「感情はコントロールできるもの」と子供が学びやすく、反対に母親が情緒不安定な状態で接していると、「感情は制御不能なもの」として認識してしまいます。
子どもが自分で感情を落ち着かせられるようになったり、お友達と適切に関われるようになったりするためにも、母親はいつも子どもに見られている意識を持っておきましょう。
愛着形成に悪影響が出る可能性がある
母親がいつもイライラしていたり、泣いていたりして情緒が不安定だと、子どもの愛着形成にも悪影響があります。

愛着形成という言葉は聞き馴染みのある人も多いと思いますが、赤ちゃんのときや小さい頃に、母親との間でつくられる心理的な絆のことを指します。
母親が日常的に情緒不安定だと、子どもにとって母親の存在は「予測できない不安なもの」になってしまい、安心や信頼の気持ちが育ちにくくなります。
たとえば、母親が日によって優しかったり怒りっぽかったりする場合、子どもは「今は近づいても大丈夫?」「自分のせいで怒ってるの?」と混乱します。
このような不安定な環境だと、子どもが心の安全基地として親を頼れなくなり、人間関係全般に不安を抱きやすくなります。
実際に母親の情緒不安定や抑うつ状態は、子どもの愛着形成を不安定にするという研究結果もあるのです。
家庭の雰囲気が子どもの安心感に直結する
これは想像しやすいと思いますが、家庭内の雰囲気は子どもの安心感に直結します。
先ほども安全基地について説明しましたが、家庭は子どもにとって一番安心して過ごせる場所であるべきです。
家庭の雰囲気が悪いと、子どもはいつも周りを気にして、心を休めることができません。

大人も気を遣う環境や、いつ怒られるか分からない場所に居続けるのは、ストレスですよね。
常に気を張っている状態や緊張した状態は、心と身体の健康にも悪影響を与えてしまうため、家庭内の雰囲気を悪くしないよう気を付ける必要があります。
過干渉や無関心は発達のリスクになる
情緒が不安定な母親は、子どもに対して「過干渉」や「無関心」になってしまうケースがあり、子どもの学習や発達の機会を妨げる原因となります。

子どもが新しいことを学んだり、社会性を育てたりするためには、「安心して失敗できる環境」や「自信を育てる関わり」が必要です。
たとえば、過干渉な母親であれば、子どもを心配するあまり子ども自身で解決しなければならない問題を代わりに解決して、成功体験を奪ってしまうことがあります。
これでは、子どもはいつまでも経験を積む機会が得られず、自分で問題を解決できないまま大人になってしまいます。
「優しい虐待」という言葉もあるように、無関心だけでなく過干渉も、子どもの発達に悪影響を与えるのです。
ストレス環境が脳や神経の発達に影響する
「前頭葉」「前頭前野」という言葉は、子どものスマホ問題から最近触れられる機会が増えてきましたが、ストレス環境も「前頭前野」や「扁桃体」へ影響を与えることが明らかになっています。
- 前頭前野(前頭葉)…理性や感情調整に関わる
- 扁桃体…恐怖や不安といった感情に関わる
ストレス環境に長くさらされると、ストレスホルモンが分泌されて、前頭前野や扁桃体の発達に影響を及ぼします。

母親の情緒が不安定だと、子どもは「安心できない環境」にずっと居続けなければならず、ストレスホルモンが分泌されて学習能力にも影響を与えるのです。
子どものホルモンや神経発達にも母親の情緒は深く関わり、心や行動の土台作りに悪影響があることを理解しておきましょう。
母親の不安定な感情が子どもに向かってしまう理由
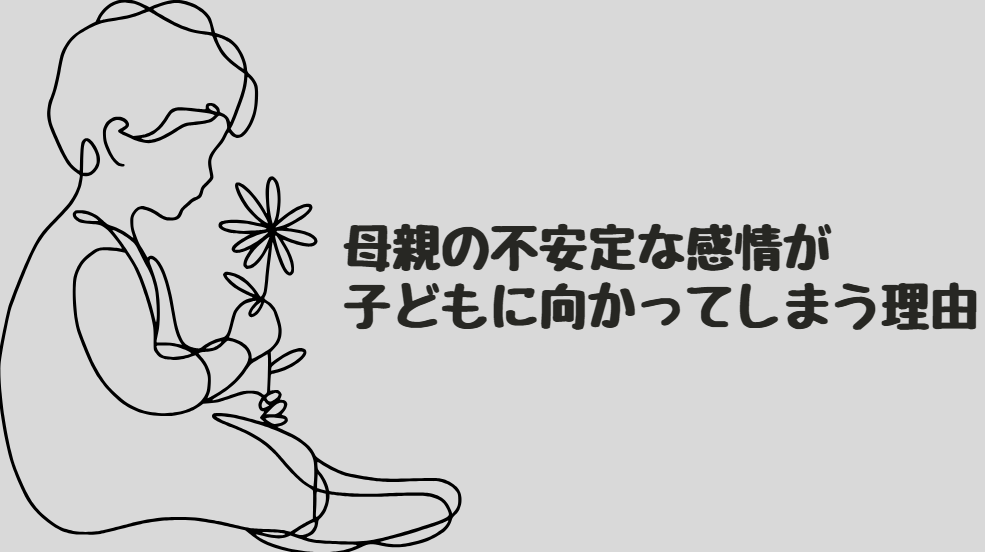
子どもに自分の不安定な感情をぶつけてはいけないと分かっていても、どうしても当たってしまうことってありますよね。
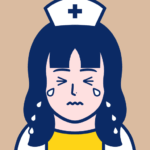
私もイライラして、子どもにいつもより強く当たってしまった後に、
「強く言い過ぎちゃったな」
「かわいそうだったかな」
と反省することが多々ありました。
「育児中の母親は孤独」といわれる機会があるように、母親にとって一番身近な存在は子どもであり、「子どもとのコミュニケーションが唯一の人との関わり」というケースも少なくありません。
そうなると、母親にとって子どもが唯一感情を表現できる相手となり、そのストレスが子どもへの過干渉やイライラ、叱咤という形で表れてしまうことがあります。
特に疲れや孤独、不安や自己否定の気持ちが積み重なった中では、誰でも感情のコントロールが難しいです。
「感情を子どもにぶつけてしまう=ダメな親」ではなく、
「今、自分はイライラしているんだな」
「今日は疲れているんだな」
と自分の感情に気付いてケアをしてあげると、子どもに当たってしまう頻度も減らせるでしょう。
情緒不安定になったときの子どもとの接し方【5つのポイント】
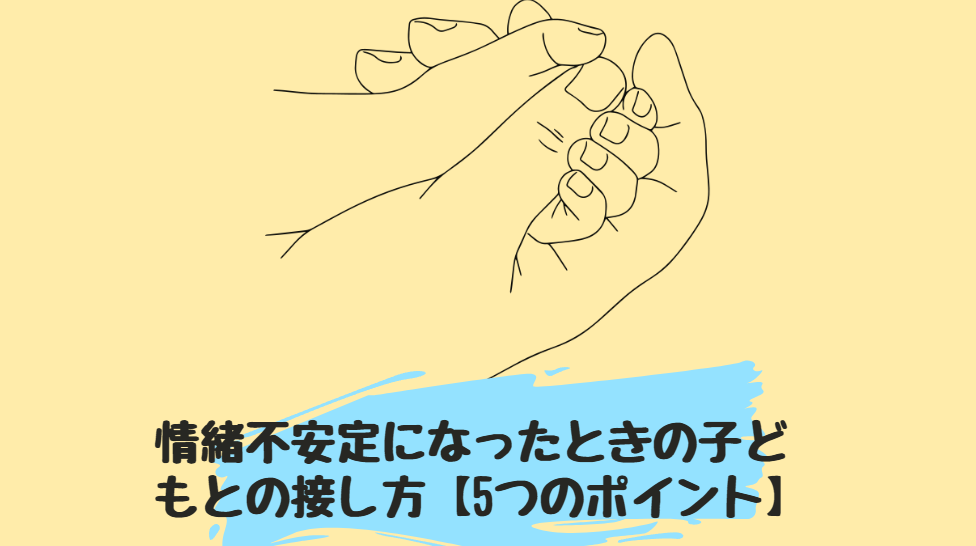
自分の情緒が今どういう状態なのかわかっていても、
「じゃあ、どうやって接したら良いの?」
「もし子どもに当たってしまった後は、どうすれば良いの?」
という疑問は、なかなか解決できません。
次の内容では、医学的な根拠をもとに、子どもとの上手な接し方をまとめました。
情緒が不安定になりやすい母親に限らず、どんなベテランママでも、子育てに悩みは尽きません。
「正解はない」ことを念頭に置きつつ、参考にしてみてください。
- 「感情」と「行動」は切り離して考える
- 気持ちが高ぶったら一時的に距離を取る
- 子どもが安心する言葉を伝える
- 落ち着いた後はフォローする時間を持つ
- 子どもを感情のはけ口にしない意識を持つ
【ポイント】子育てにおける基本的なスタンスを知る

子どもとの接し方のポイントを確認する前に、まずは子育ての基本的なスタンスを理解しておきましょう。
子育ての基本スタンスは、1つです。
それは、「感情を見せること自体が悪い」わけではなく、「感情の伝え方が大切」ということです。
子どもは母親の言葉にとても敏感で、母親の怒りや不安を「自分のせい」だと思ってしまいます。
子どもが母親の言葉に敏感なのは、それだけ母親を大切で大好きな存在だと認識してくれているからです。
感情が高ぶったとしてもこのことを思い出せば、きっと言葉の伝え方が変わってくるため、心の隅に置いておきましょう。
「感情」と「行動」は切り離して考える

上記の基本スタンスを踏まえたうえで、次は情緒不安定になったときの子どもとの接し方について、ポイントを説明します。
1つ目のポイントは、「感情」と「行動」を切り離して考えることです。
たとえば、子どもの言動に腹が立ってしまったとき、それをそのまま「無視」や「怒鳴る」、「脅す」という形で表現してしまうと、子どもは母親に対して安心感を持てなくなってしまいます。
イライラしてしまったときは、
「ママは今ちょっと悲しい気持ちなんだ。でもあなたのことが大好きな気持ちは変わらないよ」
などと、落ち着いて気持ちを伝えてあげるように意識してみてください。
ここでの注意点は、母親が無理に自分の感情を抑え込み我慢するのではなく、「母親も感情を持った1人の人間」であることを子どもに正直に見せてあげることです。
気持ちが高ぶったら一時的に距離を取る
2つ目のポイントは、自分の感情が爆発しそうになったときは、その場から少し離れてクールダウンをすることです。
アンガーマネジメントでも、「6秒ルール」が言われています。
これはカッとなったとき、すぐに感情を爆発させるのではなく、6秒間待ってから相手に言葉を伝えたり、アクションする方法です。

私も慣れるまでは、
「6秒なんて待ってられない!」
「分かってはいるけど、つい爆発してしまった!」
ということが多々ありましたが、一度実践してみると不思議なほど感情が落ち着きました。
このときに、
「ちょっとだけ1人になって落ち着きたいの。あとでちゃんと話そうね」
などと伝えられると、子どもに「感情の扱い方」を見せる良い機会にもなります。
カッとなってしまったときは、1度試してみることをお勧めします。
子どもが安心する言葉を伝える
3つ目のポイントは、情緒不安定なときこそ、子どもが安心できる声かけをすることです。
なぜなら、母親が情緒不安定なときは、子どもも不安定な気持ちになりやすく、ここで安心できる言葉をかけられると、子どもの自己肯定感を保つことができるからです。
たとえば、「今はちょっとしんどいけど、あなたのことはちゃんと見てるからね」
などの言葉があるだけで、子どもは安心してくれます。
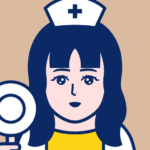
情緒不安定なときだからこそ、子どもには
「大丈夫だよ」
「大切に思っているよ」
と伝えてあげるようにしましょう。
落ち着いた後はフォローする時間を持つ
4つ目のポイントは、感情が落ち着いたら子どもをフォローする時間を持つことです。
もしイライラや涙を見せてしまった後は、「なぜそうなったか」「あなたのせいじゃないこと」をしっかり説明しましょう。
この姿勢を見せることで、子どもに「人は間違えるけど、修復できる」ことを学ばせられます。
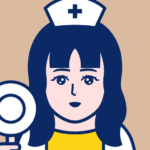
たとえば、
「さっき怒ったのは、自分が疲れていたから。あなたが悪いからじゃないよ。」
と伝えてあげられると良いですね。
感情を抑えきれずに子どもに当たってしまうと、自分を責める方向に目が向きがちですが「仕方がない」と割り切って、その後のフォローに集中しましょう。
子どもを感情のはけ口にしない意識を持つ
最後のポイントは基本的なことですが、子どもを感情のはけ口として利用しないことです。
一緒に過ごす時間が長いと、その分子どもに八つ当たりしてしまうことがあります。
しかしそれが続くと子供は、「自分は悪い子だ」と思い込んでしまうようになります。
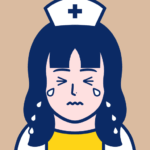
あなたも仕事やプライベートの人間関係で、やつ当たりをされたり、感情のはけ口にされたりしたら悲しいですよね。
子どもだからといって、感情のはけ口にしても良いという理由は決してありません。
もし精神的に苦しくなったときは、文章で書き出す、支援機関や信頼できる人に話を聞いてもらってストレス発散するのも重要です。
【子ども目線】情緒不安定な母親にどうしてほしかった?
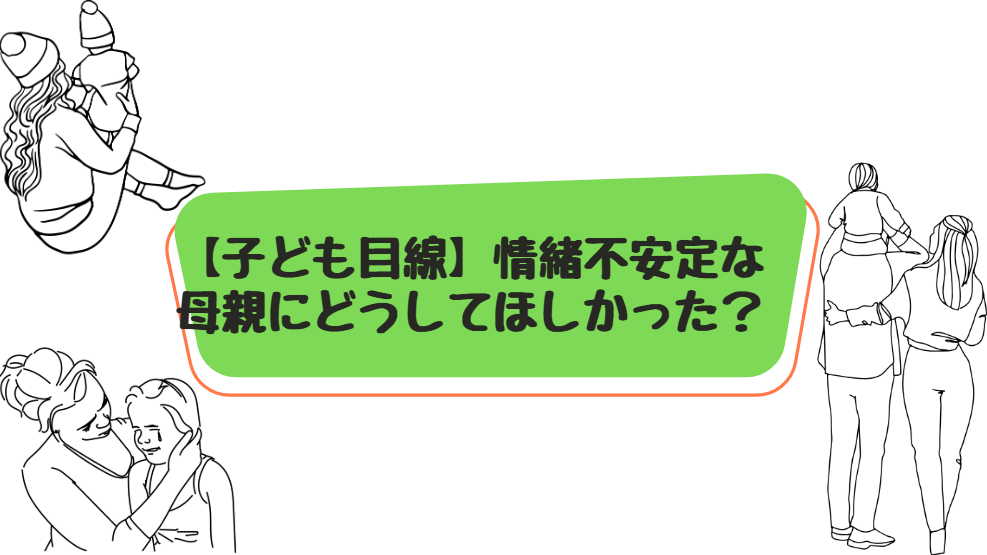
情緒不安定な母親や、毒親といわれる親に育てられた経験がなければ、幼少期に子どもがどう感じているのか想像するのは難しいです。
そこで次の内容では、実際に毒親と呼ばれる母親や、情緒不安定な母親に育てられた人たちの口コミや友人の話から、子どもの頃に思っていたことや感じていたことを聞いてみました。

私も話を聞く中で、「子どもは身体が小さいだけで、感じていることは大人と同じなんだな」と気付けました。
以下の内容を読むと、子どもが「小さな大人」といわれる理由も分かるので、自分がされたらどう感じるのか想像しながら確認してください。
子どもが母親に感じていたこと
実際に体験談を聞く中で、子どもが母親に感じていたことを箇条書きでまとめました。
- いきなり怒鳴られるとびっくりするし、何が悪かったのかわからない
- 怒る前に「ママ今疲れてる」と教えてほしかった
- ママが泣いたりイライラしたりするのは、自分が悪いからだと思ってた
- 昨日は笑ってたのに、今日は無視される…、それが一番つらかった
- 自分のことは大事じゃないんだ…と感じていた
いずれも共通点として、子どもの自己肯定感が低くなり、
「ママに大事にされていない」
「ママは自分のことなんて、どうでもいいんだ」
と感じて、母親への不信感が募っていました。

大人も仕事で理不尽に怒られたり、家庭内で責められ続けていると、
「自分はダメな人間なんだ」
「自分は普通のこともできないんだ」
と自己肯定感が下がってしまいますよね。
子どもにもこれと同じ現象が起こり、母親に対して不満を募らせていきます。
本当は大切に思っているのに、それが子どもに伝わっていないのは、とても悲しいことです。
気持ちのすれ違いを防ぐためにも、先述した「子どもと接するときの5つのポイント」を今日から少しずつ実践していきましょう。
大人になって振り返る母親との関係性
子どもの頃に母親の不安定な感情に振り回された経験がある人は、大人になってからも母親に対する不信感を拭えず、実家に寄り付かなくなってしまう人がとても多いです。
大人になってからの実家との関係性について、口コミや友人の話などから聴取した内容は以下でした。
- 母親の感情に振り回されるのが嫌なため、連絡もとっていないし帰省もしていない
- 自分も結婚や出産を通して、母親の苦労が分かるようになり、適度な距離を保ちながらも連絡を取るようになった
- 過去の出来事をすべて許すことはできないが、育ててもらった感謝の気持ちもあるため、様子確認の連絡はしている
母親としっかり愛着形成ができなかったり、安心感を得られなかったりした場合は、心理的な抵抗感や自分の心を守りたいという意識から、実家と距離を取るようになります。

反対によく帰省している人は、実家を居心地が良い場所として認識している傾向があります。
大人になってからも良好な関係を築くためには、母親が子どもの安全基地になる必要があるでしょう。
【悪影響】情緒不安定な母親に育てられた子どもが抱える悩みや特徴
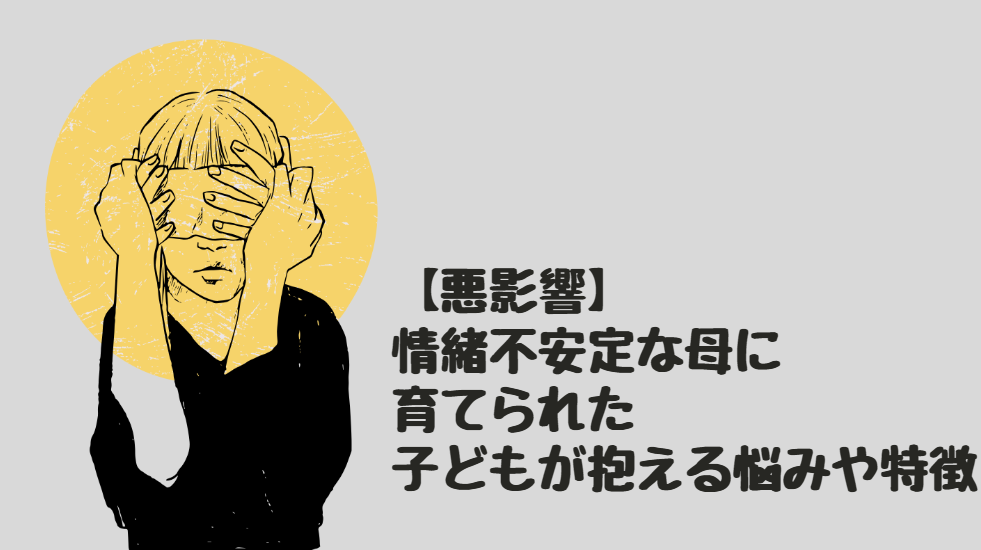
情緒不安定な母親に育てられた子どもは、自己肯定感が育たなかったり、不安障害に悩まされたりと、日常生活においてさまざまな弊害が生まれることは先述してきました。
ここでは、大人になってからも抱えやすい特徴と悩みをまとめました。
- 相手の機嫌や感情に過敏反応する
- いつ拒絶されるのか分からない経験から、不安感が強い
- 自分が本当は何を感じているのか分からない
- 人に嫌われないように過剰に配慮する
- 自分と相手の感情や責任の線引きができず、人間関係で疲れやすい
- 親しい人との関係で「急に態度が変わるのでは」という恐れを持っている
- 感情を溜め込んで突然爆発する
- 認められるために常に努力し続け、心身を消耗する
- 対立を避けるために、本音を言わず、黙って距離を置く
情緒不安定な母親のもとで育った子どもは、上記の特徴から、恋愛や結婚でも不安定な関係を繰り返したり、自分の感情がコントロールできず人間関係でトラブルになったりと、人との関わりにおいて苦労する可能性が高いといわれています。
しかしこれは、性格の欠陥ではなく、環境によって形成された生き延びるための適応反応です。
子どもにとって人間関係の基盤は母親との関係性にあり、母親と安全な関係が形成できていれば、このような問題に悩まされることは少ないでしょう。
【まとめ】母親の心が安定していると子どもの健やかな成長につながる
子どもは母親との関係性を通して「人は信頼できるか?」「自分は愛される存在か?」を学びます。
そのため、母親の心が安定していることは、子どもの成長において非常に重要です。
母親が安定していると、家庭が子どもにとっての安全基地となり、そこから外の世界に安心して挑戦できるようになります。
反対に、母親の反応が予測不可能であったり、過剰に干渉的だったりすると、子どもは人間関係に対して不安や警戒心を持ちやすくなります。

子どもが「自分の価値」を十分に感じて、「人は信頼できる」という根本作りができように母親は努めたいですね。
育児や家庭、仕事と、女性の役割はたくさんあり、気が滅入ってしまうこともありますが、上手に息抜きをしながら生活していくことが重要です。
完璧を目指す必要も、育児は母親がしなければと思い込む必要もありません。
ベビーシッターサービスや公的サービスを利用しながら、上手に子育てをしていきましょう。
ベビーシッターサービスを利用したことがない人や、うまく使いこなせていない人は、「【体験談】初めてベビーシッターを使ってみた感想と比較!信用しすぎは要注意」を参考にしてみてください。
そして母親との関わりが子どもの人生においては、「一生の人間関係の設計図」になることを忘れないでくださいね。
参考:吉田愛純,2017,「幼少期の母子関係イメージ・父子関係イメージが青年期の自立性に及ぼす影響」『中国四国心理学会論文集』50:9,(2025年8月22日取得,https://cspa.hiroshima-u.ac.jp/wp-content/uploads/2022/05/2017_9.pdf).
こども家庭庁,2025,「健やか親子21 妊娠・出産・子育て期の健康に関する情報サイト」こども家庭庁ホームページ,(2025年8月22日取得,https://sukoyaka21.cfa.go.jp/).
上野永子,2012,「母親の幼少期における愛着パターンと子育ての関連」『家族心理学研究』26(2):159-172,(2025年8月22日取得,https://www.jstage.jst.go.jp/article/jafp/26/2/26_159/_pdf/-char/ja#:~:text=%E6%AF%8D%E8%A6%AA%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82%E6%80%A7%E3%81%AF%E6%AF%8D%E8%A6%AA%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%84%9B%E7%9D%80%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8A%E6%96%B9%2C%E3%81%99%E3%81%AA%E3%82%8F%E3%81%A1%E6%84%9B%E7%9D%80%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%92%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%88%E3%82%8B%E3%80%82,%E3%81%9D%E3%81%93%E3%81%A7%2C%E6%AF%8D%E8%A6%AA%E3%81%AE%E5%B9%BC%E5%B0%91%E6%9C%9F%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%84%9B%E7%9D%80%E3%81%A8%E9%A4%8A%E8%82%B2%E8%A1%8C%E5%8B%95%2C%E6%AF%8D%E8%A6%AA%E5%BD%B9%E5%89%B2%E3%81%AE%E5%8F%97%E5%AE%B9%2C%E5%A4%AB%E5%A9%A6%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%AE%E9%96%A2%E9%80%A3%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%2C%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%82%89%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%85%88%E8%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%82%92%E6%A6%82%E8%A6%B3%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E3%80%82).