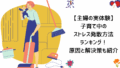「おもちゃ売り場にいくと乗り物コーナーから離れない」
「お洋服も日用品も車や乗り物の柄ばかり」
男の子の育児をしている人であれば、このような経験はないでしょうか?
乗り物にくぎ付けな様子を見て「男の子だね」と言われる機会も多いですが、男の子が乗り物好きな理由には、本能的な特性と音やスピードによる刺激が関係しています。

本記事では、男の子を育てる元小児科看護師の私が実体験を踏まえて、男の子が乗り物好きな理由やおすすめの遊び、おもちゃの選び方を紹介します。
- 男の子が車好きになる主な理由
- 男の子が車好きになる時期と続く期間
- 実践からわかった車好きな子どもの遊び方と工夫
- 実際に遊んで良かった、年齢別おすすめの車のおもちゃ
- 車好きが大人になって与える影響
- 車好きな子どもへの接し方と注意点
「こんなに車好きで大丈夫なの?」
「大人になってからの影響はあるの?」
という疑問を解決するために、参考となる情報もまとめたので、チェックしておきましょう。
【医学的根拠あり】男の子が車好きになる主な理由

男の子が車好きになるのは、以下3つの理由が関係しています。
- 動くものに本能的に惹かれる特性がある
- 音やスピードによる刺激に魅力を感じる
- 性別による差や発達段階との関係
1つ目の理由は、人間の脳は止まっているものよりも動いているものに強く反応する特性があるためです。
特に幼児期は「目で追う力(追視)」が発達する時期で、タイヤが回って進む車はシンプルに興味を引きます。
2つ目の理由は、車の「ブーン」という音やスピード感が、子どもの聴覚や視覚を同時に刺激して、ただ眺めるだけでも楽しさを感じるからです。
そして最後の理由は、男の子は「動きや構造」に関心を持ちやすく、女の子は「人や関わり」に興味を持ちやすい傾向があるためです。
この性別による差は、ホルモンや気質、周囲の働きかけや環境が原因といわれています。

必ずしも全員に当てはまるわけではなく、傾向として男の子に車好きが多いだけなので、女の子が乗り物好きでも過度に心配する必要はありません。
男の子が車好きになる時期と続く期間

男の子の車好きがいつまで続いて、いつ落ち着くのかというと、大体1歳ごろに始まり、幼児期をピークに小学生以降は個性によって「車好きが続く子」「他の興味に移る子」に分かれます。
「車好き」になるのは、ある日突然始まるように見えますが、実は成長段階に合わせて興味の持ち方が変化しているのです。
次の内容では、年齢別の興味の持ち方やおすすめのおもちゃの特徴をまとめました。

乗り物のおもちゃや日用品を買うときに、一体いつまで興味を持って使ってもらえるのか気になる人やおもちゃ選びのコツを知りたい人は、確認しましょう。
【1歳〜2歳】ミニカーに手を伸ばす時期
1~2歳は、ミニカーに手を伸ばし始める時期です。
これは、動くものや音が出るものに強い関心を示して、自然と惹かれる成長段階にあるためです。

我が家でも、寝転がってミニカーと目線を合わせて走らせたり、線路を走る電車をじっと眺めたりする姿をよく見かけました。
この時期は、以下のポイントを意識しておもちゃ選びをすると良いでしょう。
- 指先の発達を促す手のひらサイズのおもちゃ
- 音と動きを結びつける経験ができる、クラクションやエンジン音が鳴るハンドル型のおもちゃ
- バランス感覚や脚力を育てながら、車への興味をさらに高めてくれる、押し車や乗り物型のおもちゃ
ただし、よく転んだり誤飲をする可能性もあるので、誤飲の心配がない大きさか、角が丸いかはしっかり確認してから購入しましょう。
実際に私が使用して良かったおもちゃも、後ほど紹介するので参考にしてください。
【3歳〜5歳】ごっこ遊びやコレクションが増える時期
3~5歳は、ごっこ遊びをしたり、好きな車種や色を選んでコレクションしたりと、集める楽しさも出てくる時期です。
この年齢は、単なる「見る・触る」から、想像力を使った遊びへと発展します。

保育園や公園で、レースを再現したり、救急車になりきって遊んだりする姿を良く見かけますよね。
この時期のおもちゃ選びは、以下のポイントがあります。
- 物語をつくって遊べる、ガレージや道路マット、信号機などもミニカーに組み合わせる
- シリーズ展開されていて、集める楽しさが広がるミニカーやキャラクター車
- 社会や仕事への興味を芽生えさせる、救急車・消防車・パトカーなどの「働く車」
- 創造力や手先の器用さを育てる、自分で組み立てたり、色を塗ったりできるタイプの車
ミニカーやキャラクター車のコレクションで、お部屋がいっぱいになるご家庭も増えてくる時期です。
【小学生以降】他の分野へ興味が広がることも
小学生になると、車そのものだけでなく「仕組み」や「スピード」「デザイン」などへの関心が広がっていきます。
ただ「車を走らせて遊ぶ」だけでなく、知的な興味やスキルを高める要素があるおもちゃが好まれるようになるためです。

友達とゲームして遊んでいる姿をよく見かけるように、他のものに興味が移って自然と車から離れる子もいれば、中学・高校まで続く「車好き」に発展する子もいます。
車好きの小学生におもちゃを選ぶときは、以下のポイントがあります。
- つくる過程で「どうやって動くのか」「パーツがどう組み合わさっているのか」を学べる、プラモデルやレゴの車シリーズ
- 操作性やスピードの違いを体験でき、友達や兄弟と競争する楽しさが得られるラジコンカーやサーキットなどのコースセット
- 創造力や発想を伸ばすカスタムカーやデザインできる車
- 知識やコレクションを広げられる、実車をモデルにしたミニカーやシリーズ展開のおもちゃ
小学生以降は学び・創造・競争・コレクションという多面的な楽しみ方が広がります。
興味の方向に合わせて選んであげると、車のおもちゃが単なる遊具を超えて、成長のきっかけになります。
看護師目線でおすすめしたいおもちゃも、後ほど紹介するので参考にしてみてください。
実践からわかった車好きな子どもの遊び方と工夫

ここまで、年齢別の遊び方やおもちゃ選びのポイントを説明してきました。
でも、
「親子で楽しむには、どうやって取り入れたら良いの?」
「子どもと一緒に遊ぶ方法がわからない」
という人向けに、小児科の子どもたちやわが子に実践してきた取り入れ方や接し方を紹介します。

それぞれの遊び方や工夫が、子どもにどう影響を与えるのかも、根拠をもとに説明するので確認してください。
ここでコツを押さえておくと、色々な場面で子どもとの接し方に困らないようになりますよ。
ごっこ遊びで想像力を育てる
まず、「ごっこ遊び」がなぜ良いのかというと、役割を演じることで、以下のような力が鍛えられるためです。
- 相手の立場を考える「社会性」を芽生えさせる
- 遊びを通じて協調性や思いやりを学べる
- 想像力や物語をつくる力が育まれる
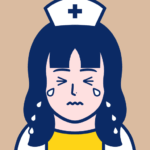
我が家では、
「痛いよー、救急車さーん、病院に連れて行ってください!」
「助けてくれるとき、救急士さんは何を思っているんだろうね」
と伝えて、ごっこ遊びを促したり、相手の気持ちを考える時間を一緒につくっていました。
このときのコツは、正解を求めるよりも
「おもしろいね!」
「いいアイデアだね」
と肯定的に返すことです。
ごっこ遊びは、大人が子どもと一緒に遊ぶ機会づくりにもなるので、取り入れてみましょう。
数字・色・形の学びに発展させる
遊びの中で、色や数、順序の学習につなげる接し方ができると、以下の効果が得られます。
- 分類や比較といった認知スキルが育つ
- 数量の概念や順序数の理解に役立つ
- 色の違いを自然に区別する練習ができる
- 「直線」「曲線」などの空間認識力が広がる

小児科の子どもたちやわが子には、
「消防車は何色かな?」
「車いっぱいあるね、何個あるか一緒に数えてみよっか!」
「トラックはどんな形してる?」
と声をかけて、自然に色や形の区別ができるように練習していました。
おもちゃで遊んでいるときに限らず、消防車を見かけたときや、列車を見かけたときなど、日頃から実践していると、より学びの機会を増やせますよ。
親子でできる「街づくり」や「道路遊び」
親子でできる「街づくり」や「道路遊び」は、親子の会話や信頼関係づくりに役立つだけでなく、以下の効果も期待できます。
- 数学的な思考力や空間を認識する力が付く
- 社会性やルールが理解できる
- 達成感や満足感、自信につながる
- 創造力や表現力が伸びる

我が家では、
「ここ、車通れるかな?」
「どうやったら車通れるようになる?」
「通れたね!すごいね!」
と声をかけて、試行錯誤した後に成功体験が積めるよう工夫していました。
街づくりや道路遊びでは、「子どもの発想を尊重しながら、親がちょっとだけ学びや社会性を混ぜる」ことを意識して関わりましょう。
【実際に遊んで良かった!】年齢別おすすめの車のおもちゃ

では実際に、我が家で使ってみて良かったものや、看護師目線でおすすめのおもちゃを年齢別に紹介します。
「おもちゃの種類が多くて、どれが良いのかわからない」
と迷うパパやママは、購入前の参考にしてくださいね。

体験談を交えながら、我が家で遊んでいた子どもたちの反応も一緒にお伝えしていきます。
他にも、車好きな男の子におすすめの絵本は、「【元小児科看護師が厳選】車好きな男の子が本当にハマった絵本(1歳・2歳・3歳・4歳別)」で紹介しているので、あわせて参考にしてくださいね。
【1〜2歳向け】安全で大きめの車おもちゃ
1~2歳は、誤飲のリスクがあるので、大きめのシンプルな車のおもちゃがおすすめです。
手押し車であれば、転ばないように安定したつくりのものが良いでしょう。
特に、「エドインターのすくすくウォーカー」や、「4wayで楽しめるベビーウォーカー」は、安全性に優れ、長く使用できます。
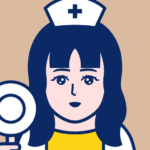
どちらも角丸設計で、誤飲のリスクがない大きさです。
特に4wayのベビーウォーカーは見た目も車っぽく、子どもの興味を引いてくれます。
たとえ飽きて使わなくなっても、収納ボックスとして利用できる点もメリットです。
【3〜5歳向け】ミニカーやサーキット遊び
3~5歳は、友達や兄弟と遊べる道路のプレイマットや、ごっこ遊びができる駐車場やガソリンスタンドのセットもおすすめです。
プレイマットは「towerのおもちゃ収納もできるプレイマット」、ごっこ遊びには「BRIOのレールセット」がおすすめです。
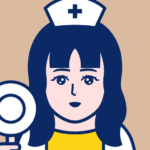
towerのプレイマットは、普段おもちゃの収納箱として乗り物を入れておき、遊びたいときはそのまま収納箱を道路にできるので、省スペースかつ効率的です。
BRIOのレールセットは我が家でも取り入れていましたが、Standard Productsなどのいろいろなお店で連結できるレールや乗り物が売られているため、部品を追加するのも簡単でした。
【小学生向け】ラジコンや工作型のおもちゃ
小学生になると、つくった達成感が得られるレゴやプラモデル、競争したり修理・調整を一緒に考えられるラジコンカーもおすすめです。
レゴや組み立てるおもちゃは以下がおすすめですが、部品が小さく誤飲のリスクがあるので、購入は必ず小学生以降の年齢で検討してください。
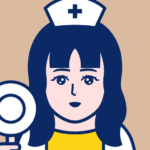
DEERCのラジコンカーは、砂地や芝の上なども問題なく走行ができ、バッテリーの持ちもよかったという口コミがあります。
レゴは息子の好きな乗り物でつくると、完成したときの感動がひと際で大喜びしていました。
車好きが大人になって与える影響
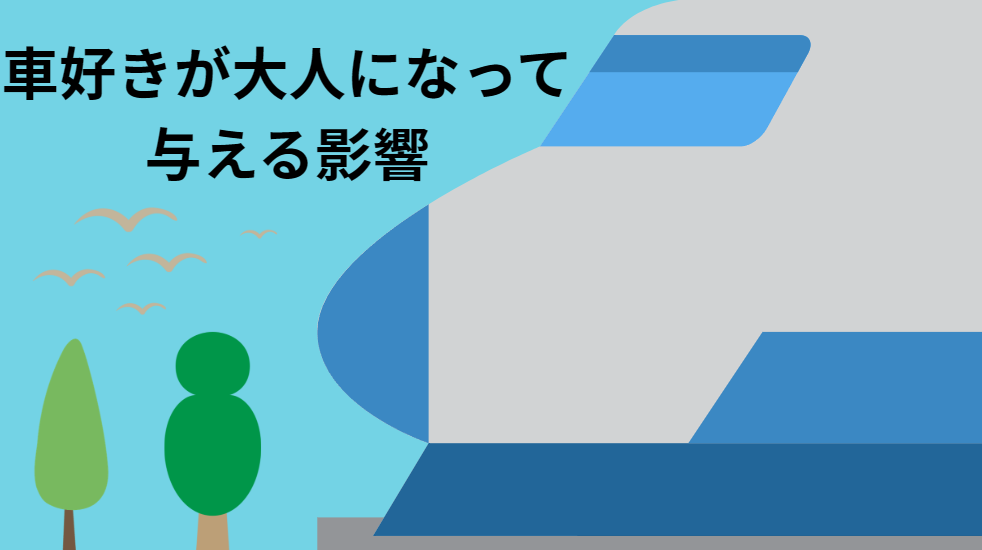
子どもが車好きだと、大人になったときにどのような影響があるのか気になりますよね。
基本的には、以下3つ良い影響があるといわれています。
- 車や機械への関心が仕事につながることもある
- 集中力や観察力がある
- 探究心やものづくりの力がある
小さいころから車のおもちゃで遊ぶと、「どうやって動くのかな?」「もっと速くできないかな?」と自然に考えるようになります。
そうすると、どうすればうまく車が走るか観察したり、早く走れるように工作したりして、その工夫の癖が大人になってからも生きるようになります。
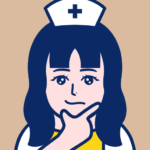
でも、大人が車好きな子どもへの接し方をちゃんと理解していなければ、そのメリットを将来活かすことができません。
次の内容では、車好きのメリットを活かすための、子どもへの接し方をまとめました。
【重要】車好きな子どもへ接するときの注意点
車好きを通して、子どもの成長や発達を促すためには、接するときの注意点が存在します。
まず1つ目は、子どもの車好きを否定したり、過度に心配しないことです。
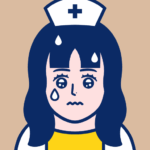
子どもが車ばかりに興味を示すと、
「うちの子は変わっているのかもしれない」
「他のおもちゃに興味を示してくれなくて、発達に問題があるのかもしれない」
と不安になるママやパパもいるかもしれません。
でも小さな子どもは、好きなものにとことん集中して、知識を深めたり安心感を得たりする特徴があります。
車ばかりに夢中になるのは「成長の通過点」と捉えて、心配し過ぎないようにしましょう。
2つ目は、車が好きだからといって、車の遊びばかりにこだわらないことです。
車にこだわると、他の遊びや経験に触れる機会が減ってしまいます。
これを防ぐためには、好きな車を「入り口」に遊びの幅を広げていく工夫が必要です。
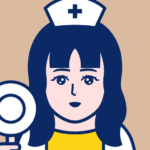
車の絵本を使って、文字や言葉に触れたり、車に積み木や人形を乗せて運んで、他のおもちゃに触れる機会をつくると良いですよ。
これらの注意点を踏まえて、子どもの車好きを活かせるように関わっていきましょう。
まとめ:車好きは成長のチャンスに変えられる
男の子が車好きな理由は、ホルモンや環境といった、いろいろな要因があります。
車が好きなのは、その成長や発達過程において自然なことで、過度に心配する必要はありません。
その気持ちを大切に、観察力や想像力につなげていけると、大人になってから子どもの頃の経験を活かせるようになります。

我が家や小児科の子どもたちを通して得た、私の体験談を参考にしながら、子どもの成長を見守っていきましょう。
参考:無藤 隆,2021,「幼児教育の基本となる乳幼児の発達と遊びと学びの特徴」,文部科学省,(2025年9月10日取得,https://www.mext.go.jp/content/20210720-mxt_youji-000016944_08.pdf).
公益社団法人日本心理学会,2008,「心理学ってなんだろう男の子が車を好み,女の子が人形を好むのはなぜ?」,公益社団法人日本心理学会ホームページ,(2025年9月10日取得,https://psych.or.jp/interest/ff-30/).
厚生労働省,2017,「保育所保育指針」,厚生労働省ホームページ,(2025年9月10日取得,https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00010450&dataType=0&pageNo=1).
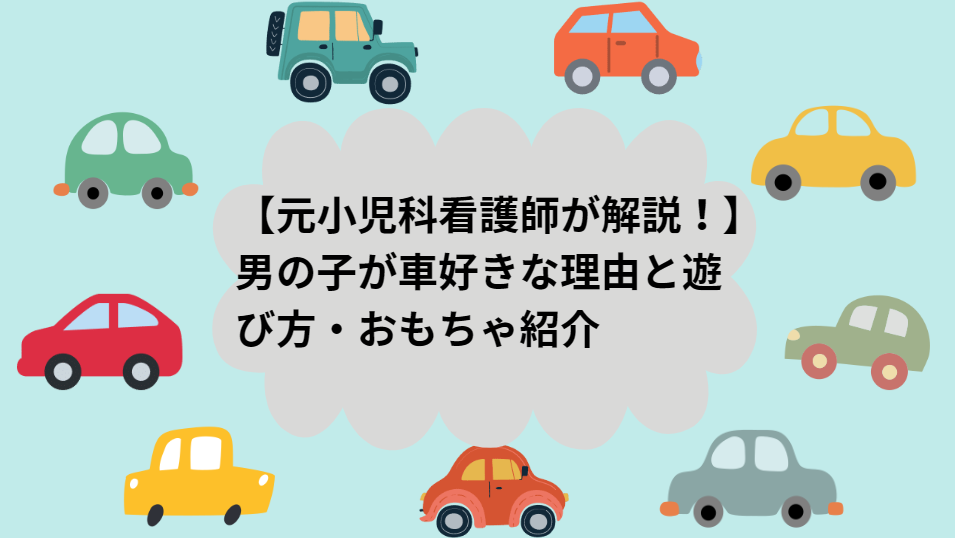
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bf6fa23.0f994f7a.4bf6fa24.6aee4008/?me_id=1226375&item_id=10003017&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbellevie-shop%2Fcabinet%2Fwear_imge3%2Ffashion113a1_2401m.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bf6fa33.aefba269.4bf6fa35.f79604af/?me_id=1395013&item_id=10001417&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fplusiine%2Fcabinet%2Fbiiino%2Ftoys%2Fbabywalker03%2Fbabywalker03-p.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3cfac199.577c0490.3cfac19a.a75b3525/?me_id=1227333&item_id=10017612&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Froomy%2Fcabinet%2F500cart_all%2F500cart_11g%2Fp5n-7%2Fymz1082-st024-0_gt01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c0a7696.06af5f79.4c0a7697.88f8f26d/?me_id=1225321&item_id=10004999&pc=https%3A%2F%2Faffiliate.rakuten.co.jp%2Fimg%2Fdefault_image.gif)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c2bdc32.48b74a58.4c2bdc33.87213a0d/?me_id=1399259&item_id=10000180&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmomoshoji%2Fcabinet%2Flego%2Fllcar%2F87525.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c2bdca6.17422d1e.4c2bdca7.176bdad0/?me_id=1313799&item_id=10000250&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-kasumiya%2Fcabinet%2Fbiiino%2Fitem%2Fmain-image%2F20251204165735_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)